バイエル画像検査室
線量管理室
DRLs 2025に対する線量管理システムの運用
2025年の7月にDRLs 2025が公開されましたが、それによって線量管理システムの運用はどう変わりますか?
基本的には大きく変わりませんが、少し注意が必要な点もあります。
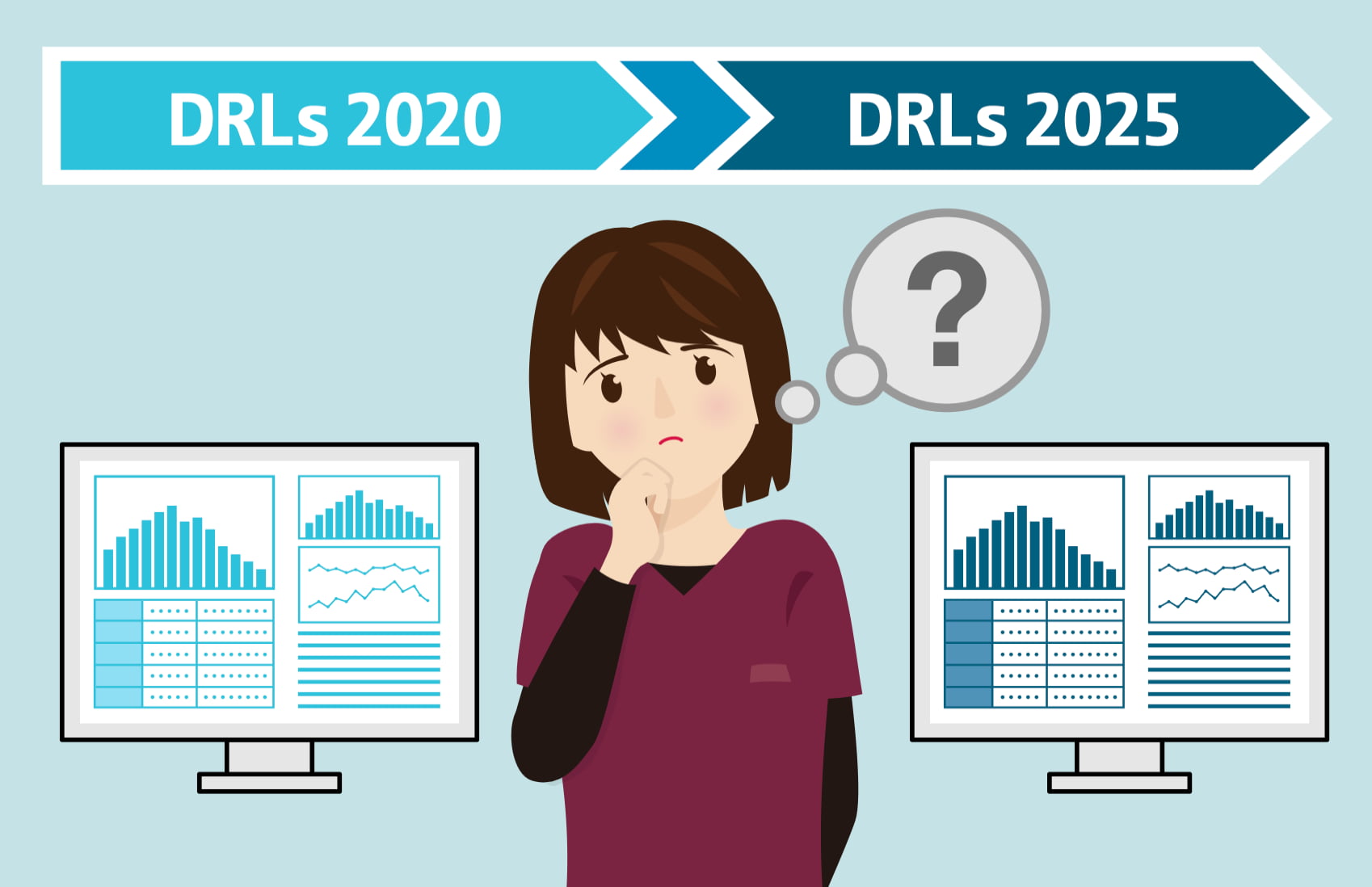
2025年7月に、診断参考レベル(DRLs 2025)が公開されました。DRLs 2020 から変更・追加された項目が複数ある中、線量管理システム側ではどのような調整が必要になるでしょうか。管理項目が増えたモダリティや、統計の取り方に注意が必要な項目において、解説していきたいと思います。
まずは診断用CTですが、成人CTにおいて冠動脈の項目に「プロスペクティブ撮影」および「単純(カルシウムスコア撮影)」での管理が追加されました。また、DLPについては以前と異なり、CTA本スキャンのみの数値を評価することとなっています。この追加に伴って、CT装置側から出力されるプロトコル名やシリーズディスクリプション等の情報を線量管理システム側で確認し、撮影単位での集計が可能であるかの確認および、必要に応じてCT装置側でのプロトコルの見直しが必要になる場合があります。
また新たな項目として、治療計画CTが追加されました。これまでは治療計画用のCT室で診断用のCT撮影を行った場合は、診断用CTに準じて線量管理を行っていたと思います。治療計画を目的としたCT撮影においても、プロトコル名やシリーズディスクリプション、スタディ名等で、目的の治療計画名が判別できるように、機器側の設定や運用方法を検討する必要があるかもしれません。
治療計画CTにおけるCTDIvolは、統計の取り方が診断用CTとは異なり、複数照射を行った際の合計値を管理する必要があります。CTDIvolの合計値が線量管理システム上では確認できない場合は、データを撮影単位でExcelなどに出力して別途統計処理を行うことも検討する必要があります。
IVRや核医学においても、管理対象項目が複数追加されたものの、線量管理システムの運用がこれまでと大きく異なるものではないため、従来の運用に加えて適宜、項目を追加していくことになります。検査装置側で管理項目を識別できるようにしている場合や、線量管理システム側で管理項目を後付けしている場合など、施設内での運用に応じた対応が必要になります。
一般撮影、マンモグラフィ、歯科X線撮影、診断透視の分野においては、医療法施行規則上の線量管理義務はありませんが、線量管理の重要性は日に日に高まっていると思われます。これらの項目については今回触れていませんが、線量管理に携わられる方々には「日本の診断参考レベル(2025年版)」に目を通し、医療被ばくの最適化に努めていただきたいと思います。
項目別に施設の代表値を集計できるようになれば、その値を新しい DRL 値と比較することで、DRLs 2025を参考にした線量評価が可能になります。まずは、現在の装置や線量管理システムの運用を確認することから始めましょう。
| 1) | 厚生労働省:診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドライン |
|---|---|
| 2) | 医療被ばく研究情報ネットワーク(J-RIME):日本の診断参考レベル(2025年版) |


